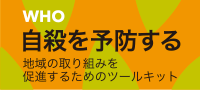自死の姿を客観的に知る。「心理学的剖検」から見えたものは?
タブーやスティグマのために科学的に向き合うことが遅れた自死。だが世界的な研究の深まりとともに、それは追い詰められた死であることがわかってきた。日本でかつて行われていた「心理学的剖検」は何を明らかにしたか。
杉山春(ルポライター)
心理学的剖検をとおして社会の環境を変える
心理学的剖検(psychological autopsy)という言葉がある。1950年代に、自殺学の父と呼ばれるアメリカの心理学者、エドウイン・シュナイドマンが作った造語だ。
「剖検」とは、死因を解明するために遺体を「解剖して検査」することを言う。法医学であれば、事件や事故の原因を探る。病理学であれば、病死の原因を探る。それを心理学的に行うのが心理学的剖検だ。
自死者の遺族などと面接をし、亡くなる直前の様子、成育歴を聞き取る。遺書やメール、ラインでのやりとりなど、故人に関わる資料を読ませてもらう。その内容を心理学的に分析し、自死の背景を理解していく。
世界的に注目された心理学的剖検に、フィンランドが1987年と88年に、1000人の共同研究者により行なった研究がある。国内の自死者の96パーセントに当たる、1397人が対象とされ、遺族や直前に接触した医療関係者への面接調査を行った。その結果自死者の93パーセントが、実行直前には「何らかの精神障害に該当する状態にあり、(中略)8割がうつ病、アルコール依存症、もしくはその両者の合併であることが明らかにされた」(『もしも「死にたい」と言われたら 自殺リスクの評価と対応』松本俊彦著 2015年 中外医学社)。同国はその調査結果に即し、強いアルコールの販売規制をかけるなど地道な対策を行い、12年間で自死者を約30パーセント減らしている。
自死予防は当事者にいかに働きかけるかに目が向きがちだが、社会の環境を変えることで自死を減らしたという結論が興味深い。
追い詰められた死
他の国々の心理学的剖検でも自死者のおよそ9割が直前には精神障害といえる状況にあったことが明らかになってきた。病的な精神状態ではしなやかな思考ができなくなるだろう。精神障害の治療という側面も自死予防には重要だ。
かつて、自死は本人の意思で行われるものだとされ、国によっては、犯罪であるともされてきた。だが、その実態が科学的に検証されるなかで、近年世界的に「自殺=自死は追い詰められた死」であると認識され、予防できると認められるようになった。
国として自死と向き合う
日本でも心理学的剖検が行われていた時期がある。
98年に自死者が3万人を超え、14年間続いた。これを受けて、政府は2001年から自死研究に本格的な予算をつけた。ことのき、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神保健計画部統計解析研究室長(当時)三宅由子氏は、直近10年間の世界の自死予防研究をレビューし、心理学的剖検に対し、「自殺の詳細な疫学研究には不可欠であると思われるが、その実施には面接者の養成や対象者の支援システム充実などの条件が必要であり、今後の検討課題であると思われる」とした。その後、06年の自殺対策基本法の成立を経て、翌年に閣議決定された自殺総合対策大綱には「社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至る経過、自殺直前の心理状態等を多角的に把握し、自殺予防のための介入ポイント等を明確化するため、いわゆる心理学的剖検の手法を用いた遺族等に対する面接調査等を継続的に実施する」の文言が入った。国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所所長(当時)の北井暁子氏の決断だったという。
この年から約10年間、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所内に作られた自殺予防総合対策センターで、心理学的剖検に関する研究が行われた。
自死遺族から話を聞くという、センシティブな課題を乗り越えるために、厳密にマニュアルや質問票を作り、第三者機関を立ち上げるなどの倫理規定を設けた。同時に、必要に応じて、弁護士や司法書士をはじめ、他機関に繋ぐことができる、遺族支援の仕組みも作った。試行錯誤の末、最終的には、東京23区内で起きた全ての不審死や自死を検案する、東京都医療監察医務院と連携が可能になる。同医務院を通じて依頼すると遺族の約3パーセントが協力した。
両立する研究と支援
当時の自殺予防総合対策センター長だった竹島正さん(川崎市精神保健福祉センター所長/国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所客員研究員)は言う。
「当初、調査は遺族を傷つけるのではないかと危惧しましたが、亡くなった数日後に、話を聞いて欲しいと連絡をくださる方もいました。急性期に、どう考えていいかわからないのですね。必要に応じて、関係機関を紹介することもありました。
私たちは、研究のための聞き取りと自死遺族支援は別のものだと思っていたのですが、必ずしもそうではないことがわかりました。それに遺族の方達も自殺予防を願っています。きちんと配慮すれば、十分に協力が得られることがわかりました」
実際に心理学的剖検を行なったのは、120例ほどだった。それぞれの事例で対象群調査を行った。住民基本台帳から故人と年齢、性別、地域が一致する人を選び、その協力を得て、最も親しい家族に遺族に対するのと同じ質問票で聞き取りを行うのだ。それにより自死をする人としない人の違いがわかりやすくなる。
同センターが行なった心理学的剖検の約3分の1を担当した松本俊彦さん(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部部長)によると、対照群調査のない心理学的剖検は、国際学会では認められないそうだ。
精神科医は自死を知らない
日本で行われた心理学的剖検は、日本の自死者の特質を具体的に示す。松本さんは次のように言う。
「つくづく覚悟の自殺は少ないとわかりました。慢性疾患を抱えている人が、決行前に治療薬が切れたというので、医者に薬をもらいに行っている。別の人は、早朝覚醒して遺書を書いたあと、コンビニに切れかかったシャンプーを買いに行き、そのあと亡くなった。進行性の神経疾患を患っている人が、決行の直前まで、自助グループのサイトと自殺の手段を教えるサイトを交互に見ていた。以前からリストカットをしていた女性のLINEを見せてもらうと、別人格が出て来ていて、解離性の障害を発症している最中に決行していました」
ほとんどの事例で、直前まで、迷いに迷うのだ。そのとき、誰かにつながり、医師につながっていたら、死は防げたのではないか。
もっとも、松本さんによると、自死者の中で既に精神科医にかかっている人たちが半分程度はいたそうだ。精神科医につながっていても、自死が起きていたのだ。
「私は医師になって、24年になりますが、系統的に、自殺リスク評価や、死にたいと言われた時の対応を教えられたことはありません。研修医のときに、指導医に自殺対応について話は聞きましたが、指導医によって、言うことはまちまちでした。指導医も系統的な教育は受けていなかったのだと思います。人生経験を元に話していたのではないでしょうか。卒後トレーニングでも指導を受けた覚えはありません。
これまでも、うつ対策として精神科に行こうというキャンペーンがありました。しかし、行った先の精神科医の系統的なスキルアップは必要だと思います」
医師の処方薬管理が自死を防ぐ
自死者の中で、処方薬を大量に飲んでいる例は少なくなかった。
「警察統計上では飛び降りや縊死と分類される事例でも、その直前に医師に処方された大量の向精神薬を飲んでいるのです。朦朧となって、死への恐怖心や自分の体を傷つけることへの抵抗感が弱まったときに決行しているんですね。その時素面だったら、死ななかったかもしれない。漫然と薬を出すことで、死を引き寄せてしまっている医師もいます」
つまり、医師による適切な処方薬の管理は、自死予防に有効だ。
「精神科医は自殺リスクの高い人たちに対して、恐れも偏見もある。多くが、対応が困難な患者を診療したがりません。なぜ死にたいのか、困難を同定して、背景に迫ることが必要です。「死にたい」の向こう側を動揺せずに聞ける度量は、精神科医をはじめとする専門家にはいき渡っていません。
一方、そうした患者を受け入れる医者は優しいのだけれど、じっくり話を聞く時間がない。医者は治したいと思って薬を出すが、それが処方薬の過量服薬になり、決行の際、背中を押してしまうんですね」
痛みには意味がある
齢者の自死に対しては、痛みは要注意だという。
「慢性リュウマチや腰痛が自殺のリスク要因であることがわかりました。痛みはADL(Active of Daily Living= 日常生活動作)に大きな影響を及ぼす。また、原因不明の痛みでいろいろな診療科をたらい回しされ、最後に精神科に来る人たちもいる。人によっては痛みによって、人と繋がりたいという気持ちがある。そのことに気がつかないと、痛みには客観的な指標がないので、痛いという言葉に従って投薬を続け、過量服薬になる場合があるんですね」
理由のはっきりしない痛みには意味がある、と松本さんはいう。
「例えば不遇な家に育ち、その家族を変えるためにかくありたいという願いを持っている。ところが、頑張っても望み通りには生きられない。理想に近づけないエクスキューズとして痛みがある。この痛みさえなければうまくいったのにと考えて生きていく人生がある。医師は、そんな患者の物語に付き合い、時には、この痛みは大変な病気なのだと、皆に知らしめる役割がある」
一方、薬を飲めないために亡くなる高齢者もいるという。
「不安感が強く、抗うつ剤が飲めない人もいる。その場合、入院をしてもらって、病院側が薬の管理をする必要がありますね」
治療として、投薬ができる医師だから、過量服薬への正しい知識が必要になるのだ。
「民間団体の中には精神科の医者なんかいらない。自殺対応は、自分たちがやるという人たちもいます。でも、ほとんどの事例で、故人は決行直前に精神を病んでいる以上、困難な事例は医者が引き受けなければなりません。そうでなければ、地域のNPOや司法書士や保健師などの支援者は安心して頑張れません。対応困難な事例を最後に引き受けるのが医療現場でなければなりません」
個人の熱意に頼るのではなく、システムによる自殺予防を
最も対応が困難なのは、SOSを出さない人だ。
「自傷的であり、自分は生きている価値がないと思っている。そういう人への支援こそ、行政がやらなければいけないことです」
酩酊状態で亡くなるという点では、アルコール問題も過量服薬の事例と似ている。
「地域の困り者の酔っ払いが病院に来る。酔っ払っているなら来るなと、叱り飛ばして帰してしまう。その帰り道、酩酊状態で怖さが飛んでいて、線路に飛び込んだということも起きる。酔っ払って受診する人は、丁寧に話しかけ、酔いが覚めてから家に帰すようにすれば、自死を防ぐことができます」
自死予防には、話を聞くこと、そして、それが必要な病状であれば、「適切に薬を出す」ことが大事だ、と松本さんは続ける。
「その場合、必要な治療薬を過不足なく、処方通りに服用してもらえるよう、周囲の理解と支援の体制を整えることも含みます。
今、医師が話を聞く時間を十分に取れないのは、医療の制度設計上、それをしたら医療機関の経営が成り立たなくなってしまうからです。熱意ある個人が経営度外視の個人的な努力で奮闘するだけでは、自死予防はシステムとして広まりません」
自死予防には制度づくりから考える必要もあるのだ。
自死の背後には困難の集積が
ところで、心理学的剖検の結果、一人の自死者の背景には、子どもの時代の虐待、いじめ、うつ、恋愛問題、家庭内の問題、子育て、職場のパワハラ、介護問題など、10以上の困難の積み重なりがあることがわかってきた。
「中高年男性の自死者は、同年齢の自殺をしなかった人に比べて、小さい時に虐待を受けていたり、いじめを受けていたりする例が多いんです。自分で自分を守ることを学べなかったんですね。そのため、職場でもパワハラの餌食になりやすい」
つまり、児童虐待やいじめへの対応は、未来の自死予防なのだ。育児支援もまた親にとっても、子どもにとっても自死予防だ。松本さんは言う。
「小さな自治体だと人員が限られる。自殺対策に力を入れるといって、それまで行ってきた酒害相談を縮小したところがありました。でも、それは残念なことです。アルコール問題は自死に強く関わります。酒害相談が自殺対策になっていたはずです」
一方、前出の竹島さんも言う。
「自死に関連する要因は複雑ですが、そのうちのリスクの1つ、2つを変えることで、自死は防げるかもしれない。また、行政が一般の公衆衛生について考えるときに、そこに自殺予防の考え方を取り入れることで、支援や予防に対する新しい工夫を生むのではないか」
自死についての的確な知識は、より有効な人材配置を生むはずだ。
知ることで減らせる死
一方、自死が起きたとき、関わりのある者同士がその理由を巡って争うことは不幸なことだ。「子どもがいじめで死んだ」場合、親と学校が裁判で争う例もある。このとき、心理学的剖検の手法が適切に働けば、関係者が無用に傷つけ合うことなく、子どもの自死を減らす手立てがみつかるかもしれない。
自死は個人的な苦しみの集積の結果でもあるが、一方で社会の変化を映す鏡でもある。心理学的剖検には社会をモニターする役割もあった。
実態から学ぶべきことはさらにあったのではないか。
現在も自死者数は2万1000人を超える。交通事故死の約5倍。交通事故を減らすために、法整備され、技術革新があった。正面から取り組むことで、事故死者数は、史上最悪の1万6000人を超えた昭和45年から、格段に減った。
だが自死は、その背後にあるタブーやスティグマのために、正面から向き合うことが遅れた。心理学的剖検に関わる研究は10年かけてようやく手法を確立しつつあったが、16年度に自死予防行政の主管が内閣府から厚生労働省に移るのに伴い、停止した。筆者は残念なことだと思わないではいられない。
なお、自殺予防総合対策センターが行なった心理学的剖検の研究は、「平成27年度障害者対策総合研究事業 中間・事後評価委員会(精神障害分野)」で、行政的評価、学術的評価、それぞれ同じ分野の21課題のなかでトップクラスの評価を得た。また、同センターは、WHO(世界保健機関)の4つ目の自殺予防の研究および研修を行うWHO協力センター(WHO Collaborating Centre of Research and Training in Suicide Prevention)として認定されていた。
執筆者: 杉山 春
雑誌編集者を経て、フリーのルポライター。著書に、『ルポ 虐待 大阪二児置き去り死事件』『家族幻想 ひきこもりから問う』(いずれもちくま新書)、『ネグレクト』(小学館、第11回小学館ノンフィクション大賞受賞)等がある。8月に『自死は、向き合える 遺族を支える、社会で防ぐ』(岩波ブックレット)を出版。
このコラムは平成28-29年度厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「外因死の背景要因とその遺族への心のケアに関する研究」によって作成したサイトに掲載されていたものです。研究代表者、著者の同意を得て、このサイトに掲載しております。